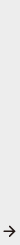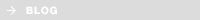三上:色々な考え方があると思いますよ。料理に例えて言えば、地元の素材を使うということがまずあります。地元の素材を使って調理場である美術館で調理して最高の料理に仕上げて来館者の方に味わって頂くということです。芸術もかなりフィールドワークのようなところがありますので、まずは足元からスタートするようにしています。
柿崎:足元からスタートしないと何も見えてこないということはあります。フェスも海外や東京で何万人も集めているものを同じやり方で仙台でやってもしょうがないわけです。そこで、フィールドワークということに興味を魅かれたのですが、地元に住んでいる作家やアーティストの方たちを発掘する時の基準というのは何かあるのでしょうか?
三上:常にリサーチをこころがけています。ある程度時間をかけて注目しながら質を見極めていくのが私たちの仕事でもあるので。そこに学芸員の存在意義があるのだと思っています。例えば、現代作家でなくとも、もう亡くなってしまって誰も知らないけれども、21世紀の現代にこの人の仕事を見せたら面白い作家、とか。
現代にどの作品が評価されるのかということを見せていくのが美術館の重要な仕事の一つだったりするわけです。ゴッホも生きている間は誰も評価しなくて、亡くなってしばらくしてから評価されました。そういう例はたくさんあると思います。その時代だったら受けないけど、今の時代だったら受けるということを提示していくのも学芸員の仕事です。
柿崎:再評価ということですね。過去とも対話し、未来にも手を伸ばすけれど、いずれも現在において光を当てるということでしょうか。時代を超えて訴えかけてくる力は、クリエイティブなものが持つ宿命のようなものでしょうか。
三上:私はアートやデザインに限らず、東北の民俗資料にも関心をもっています。名もない人が作った農具や漁具などの民具をアートの視点で見ていくと、とても面白い。素材なんてとても贅沢なものを使っているわけですよ。今では手に入らないような豊かな自然に裏付けられた素材。ものすごい太い丸太を使った木の臼なんて、今の彫刻などよりよっぽど存在感があります。そういうものを現代アートと一緒に展示したりする企画も手がけています。民具や農具といったものは、アートとは呼ばれてはいないけれども造形なんですね。名前は残ってないけれども作者がいて、それを美術館という展示空間で現代のアート作品と並列して置くことによって、共通する造形の力というものが伝わったりするわけです。
もちろん、民具や農具に芸術としてのコンセプトはないわけですが、素材の力や造形の力をまざまざと私たちに見せつけてくれます。デザインという切り口から民俗資料を見ていくと、また面白い。刺子などの幾何学模様などはモダン・デザインとしても見ることができるわけです。
柿崎:遥か昔の時代に、日常生活で使われてきたもの、生活に息づいてきたものがデザインという視点で新しく生まれ変わるというのは面白いし、とても豊かな発想という気がします。
三上:また、オブジェという視点もあります。デュシャンの便器が有名ですが。既存の何かを、それが帰属する文脈や体系から切り離して、美術展の会場に作品として置く事によって見えてくるものがあるわけです。民俗資料をオブジェとして見る事で斬新な視点を得る事もできます。
柿崎:なるほど。昔使われていた道具類などを見た時に時折ものすごい新しさを感じることがあるのですが、これはどのような心の動きなのでしょうか?
三上:アートやデザインに関心があれば気づくけれど、そうではないと見逃してしまうということがあります。アート、とりわけ現代アートに興味を持っていると新しい発見ができるのではないでしょうか。作り手側からすると、アーティストや芸術家が生まれる以前に、村々には道具を作る人々がいて、その中にも上手い人と下手な人がいたわけです。木の臼を作るにしても農具を作るにしても、きっと村の中に上手な人がいて、その人のスタイルというものができ上がって人々が受け入れて行く。しかし、スタイルができあがると当然人々は飽きてくるし、自分だけのものが欲しい人もいるので、また次の新しいものを考えていく人が出てきます。それがファッションや流行と同じ目線で見えてくるのです。
柿崎:確かに面白いですね。私たちが想定しているフェスもデザインや音楽に関心を持ってもらうきっかけになることを目的の一つとして持っています。今まで知らなかったことに対して行動を起こす引き金になるということです。今お話に出た、民具に対する視点の転換のようなことは、歴史をいったん脇に置いてモノそのものと向きあう姿勢を取ることだと思いますが、それはフェスのコンセプトにもある最新の技術についても同じことのように感じます。